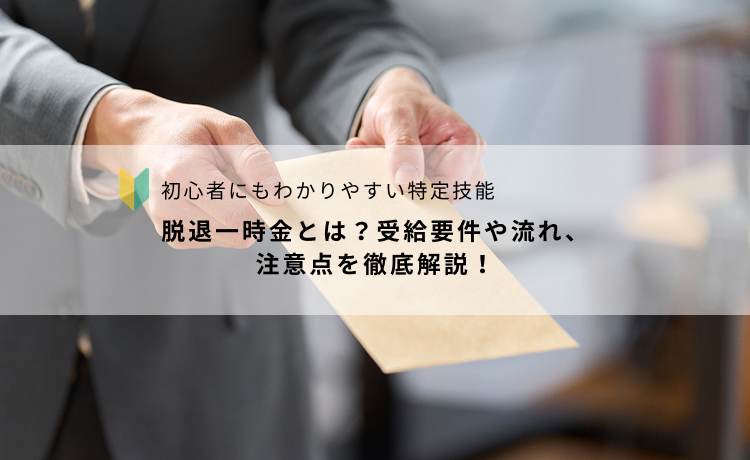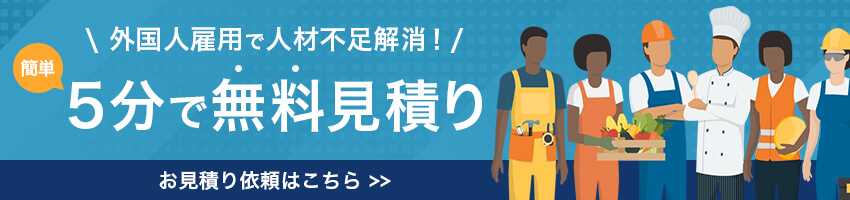「特定技能外国人は脱退一時金がもらえると聞いたけれど、脱退一時金って何?」と気になっている方はいませんか?脱退一時金はどんな外国人が受け取れる?いくらくらいもらえる?申請はどうやってやる?など、いろいろと気になっている方もいるでしょう。
そこでこの記事では、脱退一時金が受け取れる条件や金額、申請方法などについて詳しく解説します。請求時の注意点についても解説するので、脱退一時金が気になっている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
年金の脱退一時金制度とは?
国民年金と厚生年金保険には「脱退一時金制度」というものがあります。特定技能外国人も脱退一時金を受け取れる可能性がありますが、どんな制度なのかよく分からない方も多いでしょう。まずは、脱退一時金制度の概要を2つのポイントに分けて確認しておきましょう。
- そもそもどんな制度なの?
- 支給要件は何?
脱退一時金制度について理解しておくことで、特定技能外国人に受け取ってもらうかどうか検討しやすくなるでしょう。脱退一時金制度についてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。
①そもそもどんな制度なの?
脱退一時金制度は、簡単にいうと支払った年金の一部が戻ってくる制度です。日本国籍ではない外国人が、国民年金・厚生年金保険の被保険者資格を喪失して出国した場合、日本での住所がなくなった日から2年以内に限り脱退一時金を受け取ることができます。
特定技能外国人にも年金の支払い義務があります。しかし外国人は日本に在留する期間が短いことが多く、保険料を納付しても帰国して結局老後に年金の給付が受けられないことが多いです。脱退一時金制度は、そんな外国人を救済するために生まれた制度です。
在留期限まで日本で終了し、そのまま永久に帰国する単純帰国の場合はもちろん、再入国許可を得て再び入国する一時帰国の場合も条件が揃えば脱退一時金が支給されます。
②脱退一時金の支給要件は?
脱退一時金には、以下のような支給要件があります。
- 日本国籍でない
- 公的年金制度(厚生年金保険 or 国民年金)の被保険者でない
- 厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6ヶ月以上ある
- 保険料納付済期間等の月数の合計が6ヶ月以上ある
- 老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等の合算が10年間)を満たしていない
- 障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所がない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を失った日から2年以上経過していない
これらすべての条件を満たしている場合は、脱退一時金が請求できます。資格を喪失した日に日本国内に住所があった場合は、その後住所がなくなった日から2年以内なら請求ができます。
保険料の一部免除を受けた期間がある場合は、「保険料納付済期間等」は以下のように計算して保険料納付済み期間の月数と合算します。
- 保険料4分の1免除期間の月数×4分の3
- 保険料半額免除期間の月数×2分の1
- 保険料4分の3免除期間の月数×4分の1
例えば、保険料を4ヶ月4分の1免除を受けていた場合は、4×4分の3で3ヶ月納付済みとなります。免除された額が大きいほど長い期間の納付が必要になるので、免除期間がある場合は注意が必要です。
なお、年金に加入していても納付していない時期は「保険料納付済期間等」には入りません。そのため、年金加入期間イコール「保険料納付済期間等」とはならないことにも注意が必要です。
以上の注意点を踏まえ、特定技能外国人が、脱退一時金を受け取れる条件を満たしているかを確認しておきましょう。
脱退一時金の手続きと必要書類について
特定技能外国人が帰国するときにもらえる可能性のある脱退一時金ですが、どのように請求したら良いのでしょうか。脱退一時金の請求手続きと必要書類について、確認しておきましょう。
- 必要書類について
- 手続き方法
- 支給対象外となる場合
- 国民年金の脱退一時金請求書
- 厚生年金保険の脱退一時金請求書
必要書類や必要な手続きについて覚えておくと、脱退一時金を請求したいときに慌てることもなくなるはずです。脱退一時金の請求手続きについてのそれぞれのポイントについて、詳しく解説します。
①必要書類について
まずは脱退一時金の請求で必要になる書類を用意しましょう。脱退一時金の必要書類は、以下のとおりです。
- パスポートのコピー(氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格の確認できるページ)
- パスポートの出国日が確認できるページのコピー or 住民票の除票のコピー等(日本国内に住所を有しないことが確認できる書類)
- 金融機関が発行した証明書等(受取先金融機関名、支店名、支店の所在地、口座番号、請求者本人の口座名義であることを確認できる書類)
- 基礎年金番号通知書 or 年金手帳(基礎年金番号が分かる書類)
- 委任状(代理人が請求を行う場合のみ)
2つ目の日本国内に住所を有しないことが確認できる書類は、帰国前に市区町村に転出届を出している場合は必要ありません。ただ、平成24年7月以前から被保険者である場合は、提出が必要です。これは、以前日本年金機構では外国人のアルファベット氏名の管理をしていなかったため、日本年金機構でアルファベット氏名が把握できず、住民票の除票情報が確認できないからです。
3つ目の金融機関発行の証明書は、日本国内の金融機関の場合は口座名義がカタカナで登録されていなくてはなりません。また、ゆうちょ銀行や一部のインターネット専業銀行は脱退一時金の受取口座として登録できないので注意しましょう。
なお、代理人が請求を行う場合は「委任状」も必要です。代理人に請求を委任することはできますが、請求者本人が請求するよりも受け取りまでに時間がかかることがあることは頭に入れておきましょう。
②手続き方法
必要書類が揃ったら、請求者本人か代理人が脱退一時金請求書と必要書類を日本年金機構などに提出します。特定技能外国人の場合は窓口に提出するのではなく、郵送か電子申請で書類を提出します。日本の住所がなくなり出国してから2年以内に、脱退一時金を請求しましょう。
提出先は、加入していた制度や期間により異なります。日本滞在中の年金加入期間が全て国民年金か厚生年金保険のみの場合は、日本年金機構あてに請求を行います。共済組合などに加入していた場合の提出先は、以下のようになります。
- 国民年金の保険料納付済期間等が6ヶ月以上:【日本年金機構】
- 国民年金の保険料納付済期間等が6ヶ月未満:最後に加入していた雇用者年金の実施機関(厚生年金保険なら【日本年金機構】、共済組合なら【各共済組合】)
まず、国民年金の保険料納付済期間等が6ヶ月以上か6ヶ月未満かを確認します。6ヶ月以上の場合は、その後共済組合などに入っていたとしても国民年金の脱退一時金が支給されます。そのため、手続きは国民年金を取り扱う日本年金機構で行います。
国民年金の保険料納付済期間等が6ヶ月未満の場合は国民年金の脱退一時金は支給されないので、最後に加入していた制度の機関で手続きを行います。最後に入っていたのが厚生年金保険なら日本年金機構、共済組合なら各共済組合あてに必要書類を提出しましょう。
③支給対象外となる場合
せっかく脱退一時金を請求するなら、きちんと受け取りたいもの。脱退一時金が認められずに支給対象外となってしまう4つのケースもチェックしておきましょう。
- 国民年金の被保険者である
- 日本国内に住所を有する
- 障害基礎年金、障害厚生年金などの年金を受けたことがある
- 最後に社会保険の資格を喪失した日から2年以上経過している
出国前に国民年金から脱退し、各市区町村で転出届けを提出することを忘れずに行ってください。転出届なしで再入国許可やみなし再入国許可を受けて出国してしまうと、再入国許可の有効期間が終わるまでは国民年金の被保険者扱いになるため、脱退一時金が請求できません。
また、特定技能外国人が一時帰国してまた日本に帰国して就労する場合は、年金の再加入時期に注意しなければなりません。脱退一時金の請求が受理される前に年金に再加入してしまうと、脱退一時金が受け取れなくなってしまうことがあります。年金に再加入する場合は、脱退一時金が支給されてから加入するようにしましょう。
もうひとつ注意しなければならないのは、国民年金と厚生年金保険は合算して請求ができないことです。国民年金と厚生年金保険でそれぞれ6ヶ月以上被保険者になっている必要があり、国民年金に4ヶ月、厚生年金保険に5ヶ月加入していたとしても、脱退一時金を請求することはできません。
なお、どちらも6ヶ月以上保険料を支払って被保険者になっている場合は、1つの請求書に両方記載することで両方の請求が可能です。
④脱退一時金請求書(国民年金)
脱退一時金を請求することに決まったら、脱退一時金請求書を用意しておきましょう。国民年金の脱退一時金請求書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
脱退一時金請求書は、以下の言語に対応しています。
- 英語
- 中国語
- 韓国語
- ポルトガル語
- スペイン語
- インドネシア語
- フィリピノ(タガログ)語
- タイ語
- ベトナム語
- ミャンマー語
- カンボジア語
- ロシア語
- ネパール語
- モンゴル語
これらの外国語の他に日本語も併記されているので、何が書いてあるのか分かりやすいのが特徴です。上記のリンクからダウンロードできるほか、「ねんきんダイヤル」への電話、年金事務所や街角の年金相談センター、市区町村や自治体の国際化協会などでも入手できます。
⑤脱退一時金請求書(厚生年金保険)
特定技能外国人は、特定技能ビザで働いている間は厚生年金保険にも加入しているはずです。厚生年金保険の脱退一時金請求書も、国民年金と同じものを使います。
請求書には、国民年金に加入していた期間や厚生年金保険に加入していた期間を記載する欄があるので、対応するものを正確に記載してください。加入期間は国民年金と厚生年金保険の合算はできませんが、両方に加入していた時期がある方は、1つの請求書で請求できます。対応言語も国民年金の請求書と同じなので、請求者の出身国の言語のものを入手しましょう。
脱退一時金の金額について
特定技能外国人は脱退一時金が受け取れそうですが、給付される金額も気になるところです。次は、脱退一時金の金額についてのポイントも確認しておきましょう。
- 脱退一時金の計算方法
- 脱退一時金の審査期間
具体的な金額は分からなくても、金額や審査期間についてもある程度把握しておくことで、申請も安心感を持って行うことができるでしょう。脱退一時金の金額で押さえておくべきポイントについて、それぞれ詳しく解説します。
①脱退一時金の計算方法は?
国民年金と厚生年金保険は、支給額の計算方法が違います。
国民年金
国民年金の脱退一時金の計算式は、以下のとおりです。
- 最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
「支給額計算に用いる数」は、保険料納付済期間等によって決められています。最後に保険料を納付した月が2024年(令和6年)4月から2025年(令和7年)3月の場合の「支給額計算に用いる数」は日本年金機構のホームページで確認できるので、チェックしておきましょう。
例えば、6月以上12月未満保険料を納めていた場合は「支給額計算に用いる数」は6で令和6年度時点での支給額は50,940円、60月以上納めていた場合は「支給額計算に用いる数」は60で支給額は50,940円509,400円になります。半年でも約5万円が戻ってくるので、支給対象になる場合は活用しましょう。
厚生年金保険
厚生年金保険の脱退一時金は、以下のとおりです。
- 被保険者であった期間の平均標準報酬額×支給率
なお、「被保険者であった期間の平均標準報酬額」は、以下のA+B÷全体の被保険者期間の月数で求められます。
- A 2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
- B 2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
「支給率」は、日本年金機構のホームページで確認できるので、チェックしておきましょう。
例えば、被保険者期間が6月以上12月未満の場合の支給率は「0.5」、30月以上36月未満の場合は「2.7」となります。計算式が提示されているとはいえ、計算は素人には難しいところもあります。具体的な金額を知りたい場合は、日本年金機構や登録支援機関に聞いてみるのが良いでしょう。
②脱退一時金申請の審査期間はどれくらいかかるの?
脱退一時金の申請をしたら、全ての提出書類が揃って確認事項などがない場合の審査期間は約4ヶ月です。
申請から約4ヶ月後に支払いが行われ、「脱退一時金支給決定通知書」が請求者本人宛に届きます。代理人に通知書を郵送してもらうことはできず、請求者本人の母国の住所に通知書が送付されます。もし請求者が帰国後もう一度日本に来る場合は、家族などに受け取ってもらいます。
審査期間は約4ヶ月ですが、書類に不備がある場合は確認が入るので、4ヶ月以上かかることもあります。一時帰国する予定の場合は、長引いてしまうと新たに年金に入ることができず、次の就労の妨げになってしまうこともあるでしょう。
書類が揃っていなかったり書類に正しい内容が記載されていない場合には審査に時間がかかってしまいます。スムーズに手続きを済ませるためにも、必要書類や記載内容をよく確認してから提出するようにしましょう。
■その他 -脱退一時金を申請するときの注意点等-
続いて、脱退一時金を申請するときの注意点などについても確認しておきましょう。注意すべきポイントは、以下の2点です。
- 脱退一時金請求の際の注意点について
- 2021年の制度改正で支給上限が5年に!
脱退一時金も特定技能と同じように、年々状況に合うように制度が変更されています。注意点をしっかりと押さえておくことで、混乱なく手続きを済ませられますよ。それぞれの注意すべきポイントについて、詳しく解説します。
脱退一時金を請求する際の注意点
まず、脱退一時金の申請は、慎重に行わなければなりません。脱退一時金を請求して受け取ると、それまでの被保険者期間は失われるからです。2017年(平成29年)8月から老齢年金の受給資格期間が25年から10年になり、10年以上保険料を支払っている場合は年金が受け取れるようになりました。
そして受給資格期間が10年以上ある場合は日本の老齢年金を受け取ることができ、脱退一時金は受け取ることができないので注意が必要です。この場合は、請求者が出国していても、国外で日本の老齢年金が受け取れます。脱退一時金を受け取るよりも老齢年金を受け取った方がメリットが大きいので、この場合は脱退一時金の請求は行いません。
また、日本と年金通算の協定がある国の年金加入者は、日本と相手国の年金を通算して年金が支払われることがあります。これは、両国での保険料の二重負担による払い過ぎを防ぐための取り決めです。特定技能外国人の母国の協定がどのようなものなのか、確認しておきましょう。
もうひとつ注意すべきポイントは、脱退一時金の受け取りは、所得として扱われるため所得税が発生することです。これは、還付申告を行うことで一部か全部が還付されることもありますが、脱退一時金の受け取りには税金が発生することも覚えておきましょう。
2021年の制度改正により支給上限が5年に
脱退一時金の支給上限は、これまで36月(3年)でした。しかし、2021年に制度が改正され、支給上限が5年になりました。これは特定技能1号の創設により在留期間の最長期間が5年になったり、短期滞在の外国人の状況が変化して長くなったりしていることから決定されました。
2021年4月以降に国民年金か厚生年金保険に保険料を納付していた期間がある場合は、最高で5年間分の脱退一時金が受給できます。これまでは3年分の脱退一時金しかもらえなかったのが、支給上限が5年に引き上げられたことにより、5年分の脱退一時金がもらえることになりました。特定技能の5年間分の脱退一時金はある程度まとまった額になるので、特定技能外国人にとってはうれしい変化でしょう。
企業の役割と対応で必要なことは?
脱退一時金は、日本で働く外国人を救済する制度です。しかし、脱退一時金を請求することで、10年間の老齢年金の受給資格期間のうちの一部が失われてしまうので、注意が必要です。帰国してもう日本で働かないことが分かっている場合や、10年間日本で働く予定がない場合には請求した方が良いですが、既に5年以上日本で働いている場合や日本で長期間働き続ける場合などは脱退一時金を請求するべきか慎重に考えなくてはなりません。
さらに、脱退一時金を請求するということは日本の企業を退職して帰国するということなので、たとえ同じ企業で再度働くにしても退職手続きや再雇用手続きが必要です。脱退一時金の請求を行う場合は、請求人本人に制度の詳しい説明をし、適切なアドバイスをしながら請求するのかよく確認しておく必要があります。
また、帰国するときに脱退一時金のために帰国することを請求者本人が説明できるようにしておくことも大切です。帰国するときは再入国許可・みなし再入国許可を受けて出国しますが、出国の際にどうして雇用契約が終了しているのに再入国するのか聞かれることもあるでしょう。そんなときに、脱退一時金のためと説明できると出国および再入国がスムーズになります。
建設業分野では建設特定技能受入計画の認定が再度必要?
一時的とはいえ退職したあとに再度企業に入社するためには、再入社の手続きを行わなければなりません。特に建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、入管へ再度受け入れの届出を提出する前に「建設特定技能受入計画(受入計画)」を申請して認定を受けることが必要です。受入計画の申請は、国土交通省に対してオンラインで行います。
脱退一時金のために退職して一時帰国する場合は、同じ企業で働くことでしょう。それでも、建設分野の場合は再度受入計画の認定を受けなければならないので、他の分野より手続きに手間がかかります。多くの書類を用意して再び受入計画の申請をし、もし書類に不備があれば再入国や再雇用が認められなくなってしまうリスクもあるので注意が必要です。
なお、建設分野以外で特定技能外国人を受け入れる場合でも、国土交通省への報告や再認定計画の申請が必要になります。建設分野ほどではありませんが、他のどの分野でも脱退一時金を請求するためには退職・再入国・再雇用の新たな手続きが発生することと、場合によっては再入国できなくなるリスクがあることも頭に入れておきましょう。
まとめ|脱退一時金に関するご相談ならKMTに!
脱退一時金の請求には、メリットとデメリットがあります。制度について理解し、納得のいく選択ができるように企業は特定技能外国人とよく相談して請求するかしないか決めることが大切です。そのためには、脱退一時金について理解し、特定技能外国人に詳しく説明して良い選択しを提案しながら相談していくと良いでしょう。
とはいえ、説明している間に制度の詳細が分からなくなってしまい、困ってしまうこともあるでしょう。そんなときには、特定技能の受入れ実績の高い登録支援機関に相談してみるのがおすすめです。登録支援機関KMTなら脱退一時金についての相談も受け付けますので、ぜひ一度お問い合わせください。