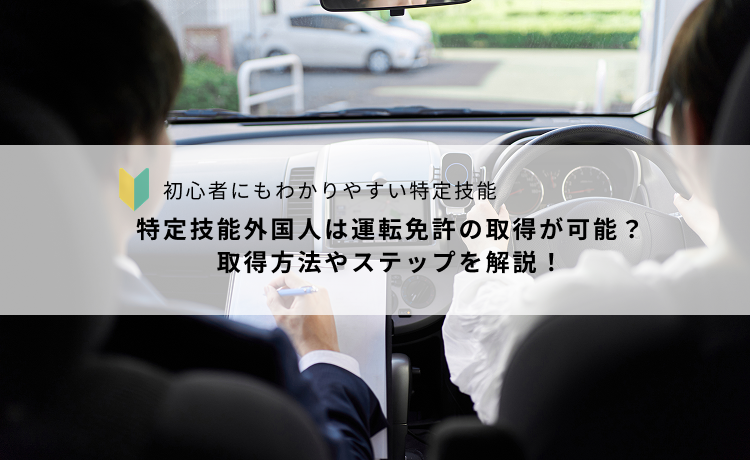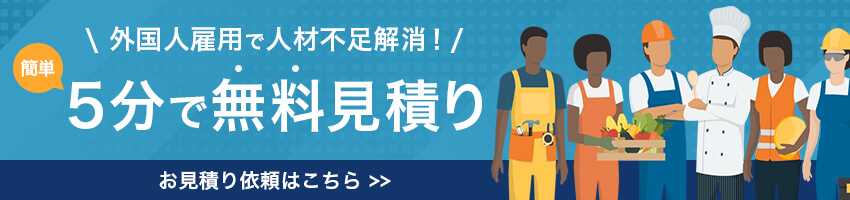「特定技能外国人って運転免許を取れるの?」と疑問に思っていませんか?「自国で運転免許を持っていたけれど、使える?」と不安になっている方もいるでしょう。特定技能外国人は日本で運転免許を取れないと考える方もいますが、特定技能外国人でも運転免許の取得は可能です。
今回は、特定技能外国人の運転免許について、取得方法や取得のステップなどを解説していきます。特定技能外国人の運転免許について詳しくなると、受入れ企業は取得へのサポートがしやすくなります。特定技能外国人の運転免許が気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
特定技能外国人が運転免許を取得するための基本知識
日本で運転免許を簡単に取得した外国人が事故を起こすケースがあり、外国人の運転免許取得方法については話し合いが進められています。特定技能外国人が運転免許を取得するためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが大切です。
- 外国人が日本で運転免許を取得する方法は?
- 特定技能外国人の運転免許取得時の注意点は?
- 運転免許取得に必要な在留資格と条件は?
まずは外国人全般について、そして特定技能外国人について、さらに必要な条件を確認すると、特定技能外国人が運転免許取得に必要なことが分かってくるはずです。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
外国人が日本で運転免許を取得する方法
まず、「国際免許証」を取得している場合は、日本上陸から1年間は国際免許証で日本で運転することができます。日本では、ウィーン条約ではなくジュネーブ条約で定められた様式で発行された国際免許証で運転が可能です。
また、スイス連邦、ドイツ連邦共和国、フランス共和国、ベルギー王国、モナコ公国及び台湾の「外国運転免許証」を持っている方も、必要な書類を提出することで日本での車の運転が認められます。これらの国や地域は国際運転免許証を発行しておらず、日本と同等レベルの運転免許制度のある国や地域だからです。
「国際免許証」や一定の国や地域の「外国運転免許証」を持っていない外国人が日本で運転する場合は、日本で運転免許を取得する必要があります。外国人が日本で運転免許を取得するには、以下の2つの方法があります。
- 切り替え
- 新規
母国で運転免許を持っている場合は、日本の運転免許への切り替えを行います。一方母国でも運転免許を持っていない場合は、日本で新規で運転免許を取得することになります。特定技能の業種として追加された「自動車運送業」で就労する場合でも運転免許は必要なので、取得しておかなければなりません。
特定技能外国人が運転免許を取得する際の注意点
特定技能外国人が日本で運送業に従事する場合は、「国際免許証」と「外国運転免許証」では日本で運転することができません。必ず日本の免許を取得する必要があるので、切り替えか新規で取得しましょう。
切り替えの場合には、母国の運転免許証の期限が切れていないことが重要です。試験を受けて合格する日も母国の運転免許が有効でなければならないので、母国の運転免許証の有効期間を確認しておきましょう。また、母国の運転免許を取得したあと、その国に3ヶ月以上滞在していることが切り替えの条件になっています。
特定技能資格を取得してから運転免許を現地で取得するなど、外国免許を取得してから3ヶ月以内に出国・来日すると、切り替えができなくなってしまうので、現地での免許取得のタイミングには注意が必要です。
運転免許取得に必要な在留資格とその条件
日本の運転免許は、長期で日本に居住する方のための免許です。運転免許取得には、在留カードか住所を確認できる住民票などが必要です。これまでは海外からの観光客などの短期滞在者も外免切替を利用していましたが、政府は今後短期滞在ビザの所有者には外免切替を認めない方針を固めました。今後、短期滞在の観光客が日本で運転するときには、外免切替による運転免許の取得はできなくなるということです。それに伴い、外免切替には住民票の写しによる住所確認が必要になります。
また、日本の交通ルールを理解していることをより良く確認できるように、外免切替の手続きは今の制度よりも厳しくなります。知識確認の設問は10問から50問に増え、90%以上の正答率が必要になります。さらに実際に車に乗って行われる技能確認での採点も厳格化されます。
特定技能や技能実習では、日本に居住していて住民票があるなら運転免許の取得が可能です。また、条件が揃えば仕事で車を運転することも可能です。留学や家族滞在ビザでも免許の取得は可能ですが、仕事として運転する場合は入管の許可を得て、許可された範囲内で運転を行う必要があります。留学や家族滞在ビザで資格外活動許可を取得し、アルバイトで車の運転をする場合は、まずは入管に許可を得るようにしましょう。
また、日本の運転免許を取得するための年齢に達していることも必須条件です。案外見落としがちですが、特定技能外国人でも普通自動車免許は満18歳以上、タクシーやバスの運転などに必要な二種免許は満21歳以上で取得できます。日本の運転免許取得時には、外国人が取得可能な年齢に達していることも確認しておきましょう。
外国免許から日本の運転免許への切り替え手続き
特定技能外国人のなかには、既に外国免許を持っている方もいるでしょう。ここからは、外国免許から日本の運転免許に切り替える「外免切替(がいめんきりかえ)」の手続きについて解説していきます。免許の切り替え手続きについて、3つのポイントを押さえておきましょう。
- 切り替えできる外国免許の条件と必要書類は?
- 免許センターでの適性検査と学科試験とは?
- 切り替え手続きの流れと所要時間は?
切り替え手続きについて知っておくことで、日本の運転免許への切り替えがスムーズになるはず。免許の切り替え手続きについての3つのポイントについて、詳しく解説します。
切り替え可能な外国免許の条件と必要書類
外免切替が可能な外国免許の条件は、以下のとおりです。
- 日本の運転免許取得年齢に達している(一種普通自動車免許:満18歳以上、2種免許:満21歳以上)
- 取得済みの外国免許が日本の免許と同等で、有効期限内である
- 外国免許取得後、その国に通算3ヶ月以上滞在していた(出入国スタンプのあるパスポートなどが必要)
そして、免許取得希者本人が申請することが必須条件です。申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 有効な外国の運転免許証
- 外国の運転免許証の日本語翻訳文(当該国の駐日大使館や日本自動車連盟(JAF)などが作成したもの)
- 日本の運転免許証 or マイナ免許証(持っている or 持っていた方のみ)
- 本籍(国籍)が記載された住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
- パスポート(外務省の発行する身分証明書、権限のある機関が発行する身分を証明する書類でも可)
- 運転免許を取得した国などに、運転免許を取得後、通算3ヶ月以上滞在していたことが確認できるもの(現在までのパスポート、過去の運転免許証など)
- 申請用写真(縦3×横2.4cm)
書類はすべて原本が必要で、コピーでは受け付けてもらえません。切り替えとはいえ手続きにはたくさんの書類が必要なので、ひとつひとつ確認しながら準備しておきましょう。
免許センターでの適性検査と学科試験の概要
外国免許が切り替え可能で、必要書類が揃っていたら、免許センターで適性検査と学科試験を受けて合格する必要があります。適性検査では、色覚や視力を確認する検査を行います。適性検査で必要な条件は、以下のとおりです。
- 普通・二輪免許:視力両眼0.7以上&それぞれ0.3以上。一眼の視力が0.3未満の方は他眼の視野が左右150度以上&視力0.7以上
- 準中型免許・中型免許・大型免許:視力両眼0.8以上&それぞれ0.5以上。三桿法の奥行知覚検査器を3回行い、平均誤差が2センチ以下
さらに外免切替希望の方は、知識確認や技能確認と呼ばれる学科試験も受けなければなりません。ただ、一定の国や地域では知識や技能確認が免除されます。知識確認と技能確認の免除を受けられる国や地域は、以下の29ヶ国です。
- アイスランド
- アイルランド
- アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州、ワシントン州のみ)
- イギリス
- イタリア
- オーストラリア
- オーストリア
- オランダ
- カナダ
- 韓国
- ギリシャ
- スイス
- スウェ-デン
- スペイン
- スロベニア
- チェコ
- デンマーク
- ドイツ
- ニュージーランド
- ノルウェー
- ハンガリー
- フィンランド
- フランス
- ベルギー
- ポーランド
- ポルトガル
- モナコ
- ルクセンブルク
- 台湾
また、技能確認のみが免除になるのは、以下の州です。
- アメリカ合衆国(インディアナ州のみ)
免除国や免除地域は変わることがあるので、警視庁のホームページで随時確認しておきましょう。
ただ、特定技能外国人の受入れ実績のある東南アジアの国々は、残念ながら免除対象外になっています。免除対象外の運転免許証から日本の免許証に切り替える場合は、運転免許試験を受験して合格する必要があります。
切り替え手続きの流れと所要時間
外免切替に必要な免許証が有効なことを確認したら、以下のステップで切り替え手続きを行います。
- 必要書類の準備
- 審査の予約(都道府県によって異なる)
- 提出書類の審査
- 適性審査
- 知識確認
- 技能確認
- 免許証交付
まずは、前述の必要書類を用意します。次に、最寄りの運転免許試験場で審査の予約をします。東京在住の方はWEB予約ができるので、活用しましょう。
その後提出書類の審査が行われ、審査終了後に視力や色覚などの適正審査を受けます。適性審査からのステップでは、既に取得している場合は在留カードも持参しましょう。また、運転に必要なコンタクトレンズや眼鏡なども用意しておきましょう。続いて知識確認が行われます。知識確認は〇×形式で、10問中7問正解で合格となる試験です。日本の基本的な交通ルールを理解しているかどうかが問われます。
その後、実技試験が行われます。実際に運転してコースを周ります。外免切替とはいえ、実技試験は普通に運転免許を取得するときと変わらないような試験です。そのため、合格率は低く、多くの方が実技試験で失格になってしまいます。すべての審査を通過し、知識確認と技能確認の両方に合格すると、日本の免許証が交付されます。
2025年現在、運転免許センターは非常に込み合っています。都道府県により混雑状況は異なりますが、審査が受けられるまでに約2ヶ月の予約待ちがあり、その予約日に審査と知識確認を行うことが多いです。知識確認は別日になる場合もありますが、知識確認に合格したら技能確認になり、技能確認までに数週間~数ヶ月ほど先になることもあります。
外免切替を行いたい場合は、外国で取得した運転免許証と在留カードの有効期限を確認し、有効期限が切れる前に運転免許を取得できるようにしましょう。
日本で新たに運転免許を取得する場合のステップ
まだ運転免許を取得したことがない方は、日本で新たに運転免許を取得することになります。日本で新たに運転免許を取る場合のステップについて、3つのポイントを押さえておきましょう。
- 学科点技能教習と試験の流れ
- 外国語対応の教習所と試験
- 合宿免許と通学免許のメリットとデメリット
初めて運転免許を取得するなら、どのように試験が受けられるのか知っておくことで安心感を持って受験できるでしょう。それぞれのポイントについて、詳しく解説します。
教習所での学科・技能教習と試験の流れ
教習所で受ける学科試験や技能試験は、日本人が運転免許を取るときと同じやり方で取得できます。以下の試験を受けて、合格することが必要です。
- 適性試験
- 学科試験
- 技能試験
適性試験は、主に視力や色覚などを検査します。実際には「運動能力検査」と「運転適性検査」があり、「運動能力検査」では視力や色覚、聴覚の検査を行います。「運転適性検査」では、いくつかの項目に答えることで、運転時の性格傾向などが分かります。「運転適性検査」で失格することはありませんが、今後の運転で気を付けることなどを確認することができます。
適性試験を受けた後は、学科試験と技能試験を受けて合格する必要があります。教習所で仮免許を取得すると、路上で運転することができるようになります。その後必要な講習を受けて、学科試験と技能試験に合格すると、本免許が取得できます。
運転免許が取得できるまでの道のりは長いので、じっくりと準備しておきましょう。
外国語対応の教習所と試験の選び方
特定技能外国人の場合は、外国語に対応した教習所や試験があると便利です。外国語で試験が受けられる言語は、以下のとおりです。
- 英語
- スペイン語
- ペルシャ語
- 韓国語
- 中国語
- ポルトガル語
- ロシア語
- タイ語
- タガログ語
- ベトナム語
- インドネシア語
- クメール語
- ネパール語
- ミャンマー語
- モンゴル語
- ウクライナ語
- シンハラ語
- ウルドゥー語
- アラビア語
- ヒンディー語
特定技能外国人に多いベトナム語やインドネシア語、タイ語などでも受けられるので、自分の国の言語が対応しているか確認しておきましょう。
ただ、都道府県ごとに外国語で受験可能な曜日が決められていることがあります。外国語で試験を受けたい場合は、各免許センターで希望の外国語で受験可能な曜日や日時も確認しておきましょう。
合宿免許と通学免許のメリット・デメリット
日本の運転免許は、通学せずにいきなり受験することも可能です。しかし、いきなり受験して合格することはかなり難しいので、教習所に通って免許を取得するのが一般的です。しかし、教習所に通う通学免許のほかに、集中的に合宿して取得する合宿免許の方法もあります。それぞれのメリットとデメリットは、以下のとおりです。
| メリット | デメリット | |
| 合宿免許 | 免許取得までの期間が短い | まとまった時間が必要 |
| 通学免許 | スケジュールに合わせて通える | 費用がかかる |
合宿免許では、1ヶ月程度で免許を取得することができます。まとまった休みなどが必要ですが、比較的低価格で受験することができます。
一方通学免許は、普通免許で約30万円くらいの費用がかかり、取得までには1~3ヶ月くらいかかります。しかし、スケジュールに合わせてじっくり通えるので、仕事や授業の合間に通うことも可能です。それぞれのライフスタイルに合った方法を選び、運転免許を取得しましょう。
特定技能外国人の運転免許取得に関するQ&A
特定技能外国人が運転免許を取得するときには、たくさんの疑問が出てくることでしょう。ここでは、特定技能外国人の運転免許取得について、気になる疑問をまとめていきます。
- 特定技能外国人の運転免許取得でよくある質問
- 運転免許取得後の業務範囲と制限は?
- 企業がサポートすべきポイントや注意点
運転免許を特定技能外国人が取得する場合は、特定技能以外の外国人が運転免許を取得するときとの違いを理解しておくと、スムーズに運転免許の取得ができるはずです。それぞれの気になる疑問について、詳しく解説します。
特定技能外国人が運転免許を取得する際のよくある質問
特定技能外国人の運転免許について、よくある質問のひとつが「自動車運送業分野」での運転免許についてです。
Q. 「自動車運送業」で特定技能1号を取るには、運転免許が必要?
A. 特定技能1号を取得して「自動車運送業分野」で働くためには、日本の自動車運転免許が必要です。具体的には、トラックドライバーは第一種運転免許、バス・タクシードライバーは第二種運転免許の取得が必要になります。さらに、バス・タクシードライバーは、新任運転者研修も修了しなければなりません。
Q. 日本の運転免許はいつ取得することになる?
A. 海外に住んでいる場合は、特定技能評価試験と日本語試験に合格して日本に入国してから、特定活動ビザで入国している期間中に外免切替か新規で日本の運転免許を取得することになります。特定活動期間は、トラックドライバーの場合は最長6ヶ月、バス・タクシードライバーの場合は最長1年間です。
一方日本に住んでいる場合は、特定技能評価試験と日本語試験に合格して現在のビザから特定技能ビザに切り替える前のタイミングで、日本の自動車運転免許を取得しておかなければなりません。
Q. 特定活動中に免許が取れなかったらどうする?
A. 特定活動中に免許が取れなかった場合は、特定技能ビザを取得することができません。特定活動を延期することもできないので、期間内に免許が取得できるようにしっかりと勉強することが大切です。
運転免許取得後の業務範囲と制限について
特定技能外国人が日本の運転免許を取得した後は、特定技能の「自動車運送業」で特定技能外国人に自動車を運転させることができます。また、付随業務として、日本人ドライバーが通常行う業務なら特定技能外国人にも従事させることが認められています。
ただ、第一種運転免許では人を乗せるバスやタクシーは運転できないので、注意が必要。バスやタクシーを運転する場合は、第2種運転免許の取得が必要です。
なお、賃金や労働時間などは、同じ会社で働く日本人と同等の雇用条件でなければなりません。外国人だからといって、低賃金や過酷な労働時間で働かせることはできません。
企業がサポートすべきポイントと注意事項
そもそも特定技能は、人手不足を補うための制度です。日本での高齢化が人手不足の原因のひとつですが、特定技能では若い外国人が数多く雇用されています。
特定技能には18歳以上でなれるのですが、バス・タクシードライバーに必要な第二種免許では21歳以上かつ普通免許等保有年数が3年以上でなければなりません。そこで活躍するのが、「受験資格特例教習」です。
受験資格特例教習を受講すると、受験資格を19歳以上かつ普通免許等保有1年以上に引き下げることができます。19歳か20歳の若い外国人をバス・タクシードライバーとして受け入れる場合は、この制度があることを説明して受講させると良いでしょう。
また、日本での運転について、外国との違いを意識させることも大切です。日本では右ハンドル、歩行者優先であることは当たり前と思っていて伝えることを忘れがちなので、注意が必要です。飲酒運転やスピード違反でも厳しい処分があることも母国とは違うかもしれないので、丁寧に説明しておきましょう。
さらに、自賠責保険に入らなければならないことや、一定期間で車検を受けなければならないことも、外国人は理解していないことが多いです。日本での自動車の制度についてもあらかじめ説明しておき、忘れることのないようにサポートすることが大切です。
企業が特定技能外国人の運転免許取得を支援する方法
受入企業は、特定技能外国人が運転免許を取得するために何ができるのでしょうか?企業が特定技能外国人の運転免許取得をサポートする方法について、3つのポイントにわけて解説します。
- 運転免許取得費用と負担方法
- 運転免許取得のための社内体制
- 運転免許取得後のフォローアップ
受入企業は、できるだけスムーズに特定技能外国人に運転免許を取得してほしいもの。支援の方法を知っておくことで、特定技能外国人の助けになるでしょう。それぞれの支援方法について、詳しく解説します。
運転免許取得にかかる費用とその負担方法
特定技能外国人が日本で運転免許を取得するための費用は、「外免切替」と「新規取得」で大きく異なります。取得費用の目安は、以下のとおりです。
- 外免切替:約1万5千円
- 新規取得(教習所に通う場合):約30万円
- 新規取得(合宿免許の場合):約20~25万円
外免切替の場合は、翻訳文の発行料や車のレンタル料も含めて約1万5千円ほど。運転免許を新規で取得するよりも、大きく費用を節約できます。
なお、運転免許取得にかかる費用は、企業が負担することが望ましいとされています。特定技能外国人が負担することもできますが、企業が負担することで特定技能外国人の経済的負担が減り、働きやすくなります。特定技能外国人の給与に、運転免許取得費用を含めることもできます。給与に含めることでも事実上企業が負担したことになるので、企業にとってやりやすい方法を選ぶと良いでしょう。
運転免許取得支援のための社内体制の整備
企業は、特定技能外国人に運転免許を取得させるための社内体制を整えておくのがおすすめです。具体的には、以下のようなことができるでしょう。
- 日本の交通ルールを学ぶ研修を実施する
- 地域の交通安全イベントに参加させる
- 日本の交通ルールを母国語で説明する or 資料を渡す
- 安全運転の講習会を開く
すべてできなくても構いませんが、できるところから始めてみると良いでしょう。現地の運転事情を知っている方が社内にいる場合は、その方に日本の交通ルールとの違いを説明してもらうのもおすすめです。研修では実際に外の道路を見ながら日本の交通ルールについて説明する機会を設けたり、イベントでは模擬運転などで運転気分を味わえる機会があったりするかもしれません。
運転免許を取りやすいように社内体制を整えておくことで、特定技能外国人が免許を取得しやすくなるだけでなく、実際に運転したときの事故の予防にもつながります。しっかりと社内体制を整え、特定技能外国人にも安全運転を定着させましょう。
運転免許取得後のフォローアップと継続的支援
特定技能外国人が運転免許を取得した後も、気を抜いてはいけません。もし特定技能外国人が「自動車運送業準備」業で就労する場合は、就労前に「新任運転者研修」を受けなくてはなりません。研修中は、「特定活動(特定自動車運送業準備)」のビザで在留することができます。忘れずに研修を受けさせましょう。
外国人は、免許を取って運転しているからといって日本の交通ルールが定着しているとは限りません。継続的に、運転ルールや救急車の通るときの対応など、日本の交通ルールを教えていくことが大切です。免許取得後のフォローアップとして、定期的に講習を受けさせることも良い方法です。
また、免許の更新も忘れてはいけません。免許を更新せずに期限切れになってしまうと免許を再取得しなくてはならくなり、手間取ってしまいます。有効期限の数ヶ月前から更新ができるので、運転免許の有効期限も確認しておきましょう。
まとめ|快適に運転免許取得をサポートしよう!
日本の運転免許は、特に自動車運送業の特定技能外国人には必要不可欠な資格です。手続きや費用などは、外免切替と新規取得で大きく異なるので、特定技能外国人が既に母国で運転免許を持っているかどうかを確認しておきましょう。
また、特定技能外国人が日本で免許を取得するには、受入れ企業のサポートが欠かせません。支援体制を整え、特定技能外国人が快適に免許を取得して活躍できるようにサポートしましょう。企業が行う運転免許の取得サポートは、登録支援機関に支援を委託することも可能です。
登録支援機関として多くの実績のあるKMTなら、運転免許の取得まで徹底してサポートします。登録支援機関にサポートを委託するなら、ぜひKMTにご相談ください。